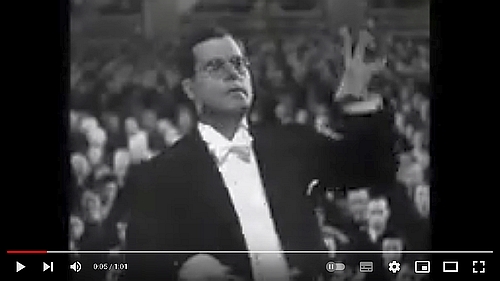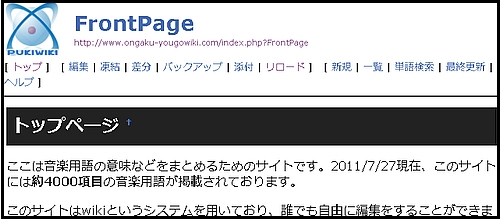人の聴覚/住環境による音質影響
- 2022/02/17 10:10
- カテゴリー:その他
- 音量の大小により、聴覚の周波数特性(周波数別の感度)は変化します。音量を小さくするほど、低周波の聴覚感度は他周波数と比べて相対的に下がります。従って、全く同じ周波数特性で、音量(振幅)が違うだけの音を聴いても、音質は全く違って聴こえます。
- 一般論として、音の良し悪しに影響を与えるパラメーターは、音量の大小>周波数特性>残響(エコー、リバーブ)です。
- 日本の住宅は、一部屋あたり一辺2m~4m程度ですが、その場合は~200hz程度までの定在波(部屋サイズと連動した共鳴)が大きく出てきます。100Hz以下の音は部屋のどこにスピーカーを置いても大して変わらず、部屋寸法とリスニングポイントで周波数特性が変わります。100~250Hzは、「スピーカー → 前壁」と「スピーカー → 後壁」の反射音が耳位置で重ね合わさるので、スピーカー位置とリスニングポイントにより周波数特性が大きく変わります。
- ある周波数の音を聴こうとすると、周辺周波数の音を下げないと、その周波数が妨害されて聴こえます。ある周波数の音が聞こえると、低周波側よりも高周波側へより強く干渉します。耳のメカ構造/センサー的な観点から説明すると、低周波の音はより体内奥側にある組織で認識します。低周波の音が耳に入力されると、その低周波に対応した耳内センサー部位に音波が達する前に、通過点にある高周波センサーに相当する組織に干渉して、高周波音の認識に影響を与えます。
- 人が聞くことが出来る音は、最も小さい音に対して、最も大きな音の音圧は100万倍=10の6乗になる。通常は対数表記して、MIN音圧を0db(SPL)、MAX音圧を120db(SPL)で表現する。3dB上げれば音圧は1.4倍、6dB上げれば音圧は2倍、10dB上げれば音圧は3倍、20dB上げれば音圧は10倍になる。個別の周波数特性を強調/減衰させる場合、精々10dB(3倍)が限界であり、20dB(10倍)も上げると、他周波数とのバランスが崩れて、歪みの大きな音になるのは直感的に分かって頂けると思う。
- イコライザー設定をする場合、32Hz以下/16kHz以上を上げすぎないよう注意して下さい。これらの音をほかの周波数と同じ音量で聞こえるほどブーストすると、難聴リスクが極めて高くなります。
※参照元ページ:
イコライザーのおすすめ設定(コツ・理論)
https://tumugi-wa.blog.jp/archives/80722202.html